■低気圧が続くと体調が崩れるのはなぜ?
「天気が崩れる前に頭痛がする」「雨の日は体が重だるい」
そんな経験はありませんか?
それは“気象病”または“天気痛”と呼ばれる、自律神経の乱れによって引き起こされる不調です。
5月下旬は気圧が安定せず、梅雨入り前の湿度や寒暖差も重なり、敏感な方ほど影響を受けやすくなります。
気圧が下がると、身体は「ストレスがかかった」と判断し、交感神経(緊張・活動モード)が優位になります。すると血管が収縮して血流が悪くなり、頭痛・肩こり・だるさ・めまい・吐き気・不眠といった症状が現れるのです。
また、内耳(耳の奥)は気圧の変化に敏感な場所。ここが過剰に反応することで、自律神経のバランスも乱れやすくなります。
■“天気のせい”にしないためにできること(セルフケア)
① 食生活:血流と自律神経を支える食べ方
-
冷たい飲み物や生野菜よりも、温かい汁物や煮物を選ぶ
-
朝は白湯やお味噌汁で体をゆっくり目覚めさせる
-
カフェインや糖分の過剰摂取は避ける(交感神経を刺激)
-
発酵食品(納豆・味噌・漬物など)で腸内環境を整える
体を内側から温めることで、血流が促され、自律神経も安定しやすくなります。
② 運動:首〜耳まわりを緩めて「気圧のセンサー」を調整
天気痛に関係が深いのが「内耳(ないじ)」という耳の奥の器官。
ここは気圧の変化を感知する場所なので、周囲が硬くなると過敏に反応します。
おすすめは、首や耳周りをゆるめる運動:
-
耳を軽く引っ張る
-
首をゆっくり回す
-
肩をすくめてストンと落とす
-
こめかみや頭皮をやさしくさする
これらを1日数回、意識的に行うことで、気圧の影響が和らぎやすくなります。
③ 睡眠:天気の乱れに負けない「夜の体づくり」
気圧の影響を受けにくい体づくりには、質の良い睡眠が欠かせません。
-
ぬるめの湯船に浸かって副交感神経を優位に
-
夜はスマホを早めに手放し、脳を興奮させない
-
アロマ(ラベンダー・ベルガモットなど)や照明を工夫
-
寝る時間・起きる時間を一定にする
「眠りの質」を高めることが、自律神経の乱れに強くなるための一歩です。
■整体師・鍼灸師ができるサポートとは?
整体では、天気痛の方に多い「首・肩のこわばり」や「背中の張り」をやさしくゆるめ、緊張状態から脱するお手伝いをします。
とくに耳周りや後頭部の筋肉をゆるめると、内耳の負担も軽減しやすくなります。
また、鍼灸では「内関(ないかん)」「百会(ひゃくえ)」「風池(ふうち)」「翳風(えいふう)」など、耳や自律神経に関係する経穴(ツボ)を使って調整を行います。
これにより、天気の変化に負けにくい“内側から整った体”をつくることができます。
■まとめ:天気は変えられない。でも、整えることはできる
気圧の変化や湿度に振り回されるのは、誰でもしんどいものです。
でも、体の反応を知り、できることを積み重ねることで「自分のコンディションをコントロールする力」が養われていきます。
食事・軽い運動・眠りの見直し、そして必要に応じてプロの手で体を調整することで、あなたの毎日が少しずつ軽くなっていくかもしれません。


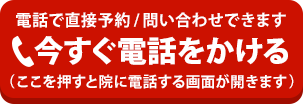
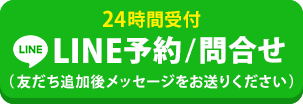





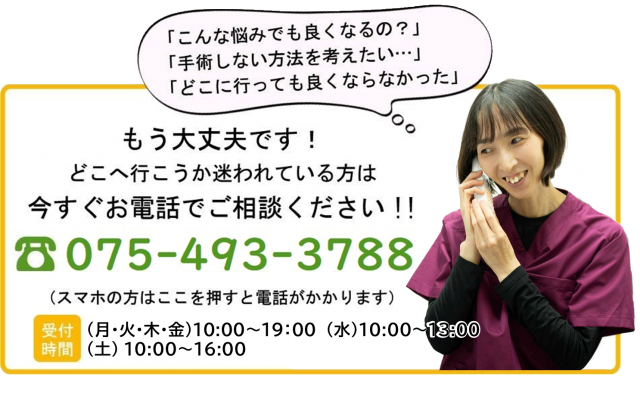

お電話ありがとうございます、
こもれび整体院でございます。