表題:朝からしんどいのは“自律神経のサイン”?
■朝からだるいのは、体がうまく休めていないサイン
「しっかり寝たはずなのに体が重い」「目覚めがスッキリしない」
そんな“朝から疲れている感覚”はありませんか?
5月の後半は、寒暖差や気圧の変化が頻繁で、知らず知らずのうちに自律神経に負担がかかりやすい時期です。
この状態が続くと、交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかず、眠っても疲れが抜けない…という状態に陥ります。
とくに、寝ている間にリラックスするはずの副交感神経が働かず、脳や内臓が“休めていない”ままだと、朝起きたときにしっかり疲れが残ってしまうのです。
■自律神経を整えるための3つのセルフケアポイント
① 食生活:冷えない・腸をいたわる・血糖を安定させる
自律神経のバランスを保つには、体を内側から温め、消化に負担をかけない食事が効果的です。
- 朝食は必ず食べる
- お粥やみそ汁、温野菜など、消化の良い温かいものを中心に
- 発酵食品(味噌・納豆・ぬか漬けなど)を取り入れ、腸内の環境を整える
- 甘い菓子パンや冷たい飲み物は控えめに(血糖値の急変動を避けるため)
とくに朝の冷たいスムージーやヨーグルトは、春の終わりには逆効果になりやすいので、常温以上のものを選ぶのがおすすめです。
② 運動:軽い動きで体内時計をリセット
朝から体が重たい日は、いきなり活動的に動く必要はありません。
まずは「少しずつ目覚めさせる」ことを意識したいところです。
- 起きてすぐ、ふくらはぎを動かす(血流促進)
- 布団の中でゆっくり伸びるだけでもOK
- カーテンを開けて自然光を浴びる(メラトニンとセロトニンの切り替えに)
- 5〜10分だけでも外を歩いてみる
座りっぱなしの仕事をしている方は、1時間ごとに立ち上がって歩く。
無理なく体を動かすことが、自律神経を安定させるカギになります。
③ 睡眠:リラックスモードに切り替える“夜のルール”
質の良い睡眠は、自律神経のバランスを整えるうえで欠かせません。
大切なのは、寝る直前だけでなく“寝る前の1〜2時間”の過ごし方です。
- スマホやパソコンの画面は、寝る1時間前にはオフに
- 間接照明やアロマを使って、視覚・嗅覚からリラックス
- 深呼吸を意識しながら軽く動かす(首・肩・腰など)
- 38〜40度のぬるめのお湯で短めの入浴
- 就寝・起床時間を毎日できるだけ同じにする
寝る時間を決めて習慣化することで、体内リズムが安定しやすくなります。
■整体師・鍼灸師としてできるアプローチ
整体では、朝のだるさが続く方の多くが「首〜背中」がガチガチに硬くなっています。
これは交感神経が過度に緊張している状態で、呼吸も浅くなり、内臓も休まりません。
私たちの施術では、首肩まわりをゆるめることで、背骨を通る神経系にアプローチ。
背中から腰、骨盤にかけての緊張も解いて、全身の血流を促します。深く呼吸が入るようになると、体のスイッチが“休むモード”へと切り替わっていきます。
鍼灸では、「百会(ひゃくえ)」「神門(しんもん)」「足三里(あしさんり)」「内関(ないかん)」など、自律神経の安定に関係する経穴を使って施術します。
また、胃腸・肝・腎といった内臓の働きを整えることで、体の中からの疲労回復を促します。
■まとめ:疲れを翌日に持ち越さないために
5月の終わりは、体も心も知らず知らずのうちに“がんばり疲れ”が出やすい時期。
朝のだるさは「まだ休みが足りていませんよ」という体の声かもしれません。
そんなときこそ、自分をいたわる生活習慣を。
- やさしいごはん
- 軽やかな動き
- 休まる夜の時間
そして、必要なときには整体や鍼灸でプロの手を借りて、しっかり整えていきましょう。


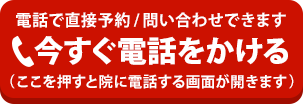
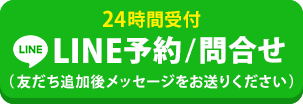





お電話ありがとうございます、
こもれび整体院でございます。