■悩みの解説:「体に湿気がたまる」とどうなるの?
5月の後半になると「なんとなく怠い」「体が重たい」「浮腫みやすくなった」と感じる方が増えてきます。
これは、東洋医学で言うところの「湿邪(しつじゃ)」が原因の一つかもしれません。
湿邪とは、梅雨時期や梅雨前の湿度の上昇する影響で体内に“湿気”がたまることで、巡りが悪くなり、消化機能や気の流れを妨げてしまう状態を指します。
特に以下のような症状がある場合は要注意です:
-
朝起きても体が重い
-
食欲がない、胃がもたれる
-
足や顔が浮腫む
-
頭がぼーっとする
これらは「体に湿が溜まっている」サインの一例です。
■解決策:湿をためない体づくりのポイント
●食生活:「水はけ」を良くする食材を意識する
おすすめは、体の“余分な水分”を外に出す作用がある食材です。たとえば…
-
小豆(あずき)
-
冬瓜(とうがん)
-
ショウガ
-
三つ葉
-
ネギ
-
トウモロコシ
-
ハトムギ
また、冷たい飲み物や生野菜の摂りすぎは✖。温かい味噌汁や煮物で内臓を冷やさないように意識的に摂取しましょう。
●運動:汗ばむ程度の「軽い運動」で湿を飛ばす
湿気が体に溜まりやすい人は、運動不足が原因の大きな要因に・・・。軽く汗ばむくらいのウォーキングやラジオ体操などが最適です。
太極拳やヨガなど、深い呼吸を意識する運動も吉。湿邪は皮膚や肺から発散されるので、発汗と呼吸を意識しましょう。
●睡眠:気圧・湿度に負けない体をつくる“早寝”習慣が◎
健康のベースは、「早寝・早起き」!湿度が高まる時期は自律神経が乱れやすいため、意識するのが基本です。夜更かしや寝不足は巡りを悪くし、むくみやだるさの原因に。22時~23時までに就寝することで、自然治癒力が高まります。「寝る子は育つ」の続きをご存知ですか?「寝る大人はやせる」です。
■整体師・鍼灸師の視点:「湿だるさ」は“脾(ひ)”の弱りからくることもある
東洋医学では、「脾(=胃腸)」が湿を嫌うといわれています。整体では骨盤の安定性を担保することで、背中・腰の筋肉が緩むように促し、内臓の働きを助ける調整を行います。
また、鍼灸では「陰陵泉(いんりょうせん)」「足三里(あしさんり)」「脾兪(ひゆ)」など、余分な水を流すツボを使い、体の巡りを整えることができます。
■まとめ
5月下旬の“なんとなく不調”は、湿度の変化に体がついていけていないサインです。
「食事・運動・睡眠」をしっかり、意識し、整体や鍼灸でサポートを加えることで、梅雨入り前のこの時期も軽やかに過ごせます。
毎日忙しく頑張っている方こそ、自分の体の“重ダルさ”に気づいたら、ひと息入れて整えてあげましょうね。


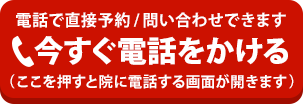
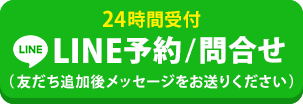





お電話ありがとうございます、
こもれび整体院でございます。